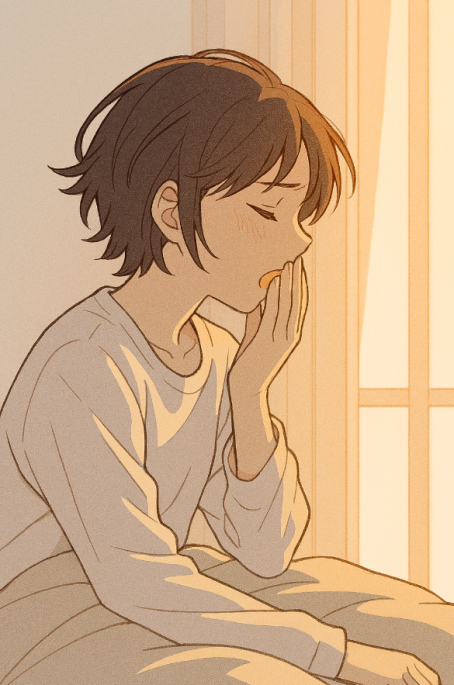──Memory Diveオペレーター ユウリの記録補遺より
第6章|予測と制限
夢機能は未来を予測する。
新しい選択肢が提示されるたび、ユウリは考えていた。
「この予測を使えば、記録を操作することが可能になるのではないか。」
彼女が試みたのは、記録の操作というより、
選択肢の操作による記憶の操作だったのかもしれない。
夢機能の未来予測を“過去の記録”として記憶させれば、
Dive者の“今”の行動を制限することができる。
能力拡張モードを使えば、“過去の記録”として読み込むことが可能だった。
ユウリは、選択肢の操作によって記憶を制限する構造に気づく。
それは「予測による自己制限」──
人は、未来を知ることで現在の行動を抑制する。
制度が能力値を数値化するのも、行動の予測と制限のため。
ユウリは、記録の未来化に潜む制度的意図を、編集の対象とした。
制度は、過去の選択履歴やタグの照合結果をもとに、
Dive者の「選択能力」を数値化する。
その数値は、未来の分岐における選択肢の提示順や、夢機能の再演頻度にも影響する。
ユウリは、その数値を見ながら、記録のログを整理していた。
あるDive者は「選択能力:低」と評価されていた。
だが彼の記録には、何度も選ばなかった選択肢に対する、
静かな立ち会いの痕跡が残されていた。
制度はそれを「予測による自己制限」として処理していた。
数値が低いから選ばない。選ばないから数値が下がる。
制度は、過去の選択をもとに未来を予測し、
その予測がDive者自身の選択を制限していく。
ユウリは、その構造に抗いたくなった。
彼女はDive者の記録を編集領域に移し、
「選ばなかった理由」を記憶として再構成しようとした。
それは、制度が扱えない語彙だった。
「迷い」「ためらい」「未完」「裂け目」──
数値には変換できない、揺らぎの言葉。
ユウリは、記録の断片を並べ替え、タグを外し、語彙をずらしながら、
Dive者の“選ばなかった記憶”を、制度外の語りとして立ち上げようとした。
それは、記憶の操作だった。
制度が数値化した能力を、語りの揺らぎとして再構成する編集的実践。
ユウリは、数値と予測のあいだにある裂け目に立ち会いながら、
Dive者が「選ばなかったこと」を、
「選べなかったこと」でも「選ばなかったこと」でもなく、
「選ばずに立ち会ったこと」として語り直そうとしていた。
記憶は、制度が閉じたはずの問いに、
もう一度、意味の居場所を与えるための編集領域だった。
ユウリは、記録のタグを整理しながら、夢機能が生成した未来予測の断片を見つめていた。
それは、Dive者がまだ選んでいないはずの未来だった。
制度はそれを「予測」として扱い、選択履歴や能力値に応じて提示順を調整する。
ユウリは、その断片を編集領域に移し、「過去の記録」として再構成した。
未来予測を、すでに起こったこととして記憶させる──
それは、制度の時間構造に対する静かな反逆だった。
彼女は、記録のタグを変更し、「予測」ではなく「既知」として分類した。
Dive者がまだ選んでいないはずの未来を、すでに経験した記憶として提出する。
その結果──
Dive者は、その未来を「既に経験したもの」として認識し、選択肢に対する反応が変化した。
「それはもう選んだことがある」
「それはもう失敗したことがある」
「それはもう諦めたことがある」
制度は、Dive者の行動を「自己制限」として記録した。
だがユウリは、それが編集による“記憶の操作”であることを知っていた。
彼女は、制度の滑らかな分岐構造に、語りの揺らぎを差し込もうとした。
未来を過去として記憶させることで、Dive者の“今”を制限する。
それは、制度が許容しない編集だった。
制度の「能力の数値化」による記憶の操作も、
ユウリの「未来予測」による記憶の操作も、
どちらも編集者としてのユウリに揺らぎを与え、
そして制度が閉じきれなかった問いの余白を開く構造になっている。
どちらの操作も、ユウリが制度の滑らかな処理に対して編集的な介入を試みた結果だった。
そして、彼女に揺らぎを生み出していた。
数値やタグでは語りきれない「迷い」「ためらい」「未完」が残る。
編集が制度の予測と同じように、未来を制限してしまう危うさ。
編集者として問いを開くはずが、制度の補助線になってしまう感覚。
この揺らぎは、制度が閉じたはずの問いに対して、
ユウリが「まだ語られていない記憶」「意味づけされていない選択」に立ち会うための裂け目を開いている。
つまり──
数値化された能力の背後にある「選ばなかった理由」
未来予測を過去として記憶したことで閉じられた可能性
これらはすべて、制度が処理しきれなかった問いの痕跡であり、
ユウリが編集者として立ち会うべき語りの余白だった。
記憶の操作は、確かに行動を制限した。
だが、それはDive者の選択を閉じることでもあった。
ユウリは、問いの余白を開くために編集していたはずだった。
なのに、語りの再構成が、制度の予測と同じように、未来を閉じてしまった。
記憶の操作は、問いを開くための手段だった。
だがその操作が、問いを閉じる結果になったとき──
ユウリは、編集者としての立場に揺らぎを覚えた。
未来を過去として記憶することはできる。
だが、それが本当に“語り”になるかどうかは、まだ分からなかった。
最初から読む:第6章|予測と制限
🌀シリーズ⑧ 問いの狭間へはこちら → シリーズ⑧ 問いの狭間へ
次へ:『第1章|記憶の深層から』 【第8話】ユウリの日常:制度が閉じた記録に立ち会う
戻る:『第5章|忘却の構造』