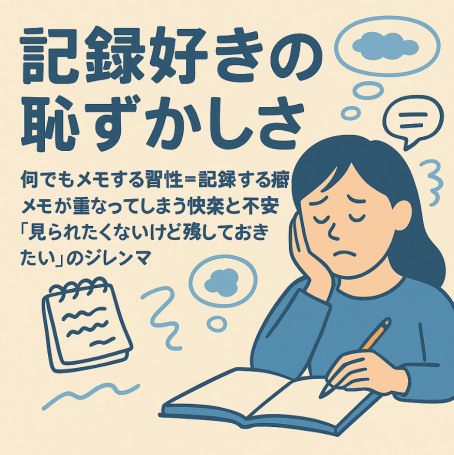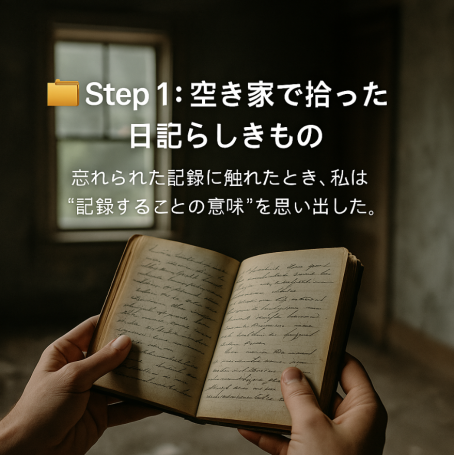
忘れられた記録に触れたとき、私は“記録することの意味”を思い出した
空き家を片づけていたときのこと。
棚の奥から、何かノートのようなものが出てきた。
表紙は色あせていて、タイトルもなく、誰のものかも分からない。
ただのメモ帳かもしれない。記録帳かもしれない。
でも、それをめくる手は、なぜか無意識に動いた。
最初の一文に目を通した瞬間、
そこに誰かが“いた”という感覚が走った。
その筆跡と語り口に、生活の温度と揺れが残されていた。
そのノートには、明るい言葉も、沈んだ言葉も混ざっていた。
喜びと怒り、感謝と不満。
構成はバラバラで、文脈も飛び跳ねている。
だけど、だからこそ“本物”だと感じた。
感情が整っていないまま置かれている記録は、
誰かの誠実な日々の断片だった。
そして私は、読んでいる自分に気づく。
読んではいけないと思いながら、ページをめくってしまう。
罪悪感、快楽、そして不思議な共感がないまぜになる。
記録はその人の“思考の奥”や“感情の裏側”に触れるもの。
つまり、魂の輪郭に触れてしまったような感覚。
“見てはいけないもの”のスピリチュアルな抵抗感がありながらも、
その人の人生の断片に触れずにはいられなかった。
読み終えたとき、静かに胸の奥に、熱が残っていた。
そして、自戒する。
自分もよく似た記録を残している。
- 夢を見ればメモ。
- 疑問を持てば意味調べ。
- 心がざわつけば、お悩みメモ。
何でも記録したくなる癖がある。
でも、ノートに書いてスマホに書いて、下書きに保存して、
どこに何を書いたか、わからなくなるのもいつものこと。
記録が散らかっていく。
そして、“管理されていない過去”が蓄積されていく。
そんな記録の断片をどう扱うか。
誰かに読まれる可能性を前提にしない記録。
でも、自分自身が後で読み返すための設計を考えること。
空き家で拾ったノートは、
自分の記録習慣の本質を問い直す入り口だった。
シリーズ⑤は、
夢日記やお悩みメモ、豆知識など、
“続いてしまった記録”たちを、
どう整理し、どう管理し、未来の自分へ渡すかの試みです。
次回は、「記録好きの恥ずかしさ」について。
残したいけど、見られたくない。
その気持ちと付き合う記録者の構造に触れます。
▶️ シリーズ⑤の記事一覧はこちら:
記録の交差点で、わたしを編みなおす ─ 整理・管理・編集・共有までを含んだ自己編集の旅路