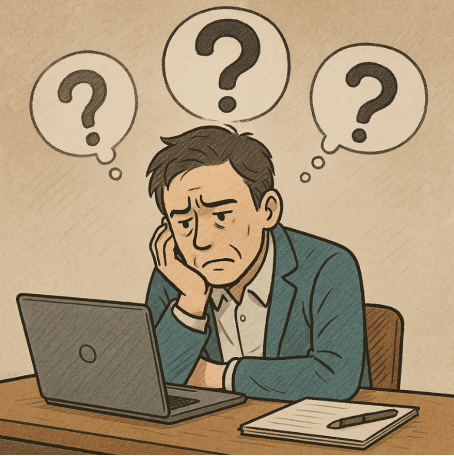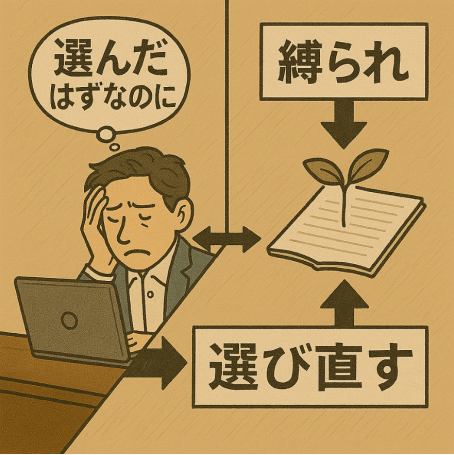なるべく効率的に過ごしたい。
ムダなことは避けたい。
合理的に、最短ルートでたどり着きたい。
そう思って選び方を磨いてきたつもりだった。
けれど──「効率を求めるほど、非効率になっていく」そんな矛盾した感覚を抱えるようになった。
🧭 効率化の罠──吟味しすぎて、動けない
何かを始める前に、考える。
- それは今やるべきことか?
- それをやることで何が得られるか?
- もっと効率的なやり方はないか?
その思考は、たしかに“良い選び方”のように見える。
でも、考えているうちに──動けなくなる。
吟味すればするほど、“やる理由”が見えづらくなる。
どれも中途半端に感じて、全部後回しになっていく。
それは、いつしか「何もやらない自分」へと変わっていった。
🔍 やらない理由に言葉を与えることで、“納得”が生まれた
「やらない自分」を責めていた。
けれど、ある日、紙に書いてみた。
- 今日やらなかったこと
- やらなかった理由
- どう感じていたか
そこには、「やりたくない」「目的がぼんやりしている」「別のことに気を取られていた」などの言葉が並んだ。
その瞬間、“やらない理由”がただの怠惰じゃなくて、自分の状態の記録に変わった。
言語化することで、自分の選び方に“納得”が宿る。
やらなかったことにも意味があると、初めて思えた。
🌀 非効率に見えることこそ、意味のある道かもしれない
散歩、雑談、寄り道、検索の脱線──効率だけで見れば、どれも“ムダなこと”かもしれない。
でも、気づく。
その中で気持ちがほぐれたり、問いが生まれたりすることがある。
むしろ、「最短ルート」の中には、そんな余白がない。
非効率に見える行動の中に、意味が宿るときがある。
「ムダかもしれないけど、やってみたい」──その感覚が、今の自分に必要だったりする。
📚 インプットの効率が「考えること」を止めるときもある
知識を増やしたくて、検索や読書を重ねていた。
でも、あるとき気づいた。
“借りてきた言葉”で頭の中がいっぱいになっていた。
何かを考えるよりも、“考えた気になっている”状態になっていた。
効率よく情報を拾えば拾うほど、自分の「なぜ?」が止まっていく。
インプットは大切だけど、それが“自分で選ぶ感覚”を奪ってしまっては、本末転倒だ。
💭 “やらないこと”にも納得があれば、止まっていない
「なんであれをやらなかったんだろう」「なんで今日は動けなかったんだろう」そんな問いが浮かんだとき、書いてみる。
そうすると、“やらないこと”に意味が出てくる。
それは、無駄な時間ではなく、選ばなかった時間になる。
やらない理由に納得感があれば、それは、止まっていたようで、実は前に進んでいた時間になる。
🧩 効率化より、“選び直せる感覚”を持ちたい
今の自分にとって大切なのは、効率よく生きることじゃなくて、「自分で選び直せる感覚を持つこと」だった。
やらなかったことに意味をつけられたら、非効率な時間にも、豊かさが宿る。
効率を求めすぎて動けなくなるくらいなら、ちょっと遠回りでもいいから、納得できる選び方をしたいと思っている。
📌 次回予告:
番外編⑩|「自分で決めたはずなのに、従っている感覚」──選び直す自由はどこにある?
自由に選んだはずなのに、いつの間にか縛られていた。「選び方」と「従属感覚」の間にある違和感を言語化していきます。
番外編⑩|「自分で決めたはずなのに、従っている感覚」──選び直す自由はどこにある?
📎 関連する記事一覧表|番外編⑨とのつながり
| 記事タイトル | 関連テーマ | リンク |
|---|---|---|
| 番外編⑥|「続ける理由が消えていく」──やめたい気持ちと、やめずに残るもの | 続けることへの疑問/やめることの納得と難しさ | 読む |
| 番外編⑧|「好きだったはずなのに、続けられない」──やめたくなる自分との付き合い方 | 行動が止まる理由/好きだったこととの距離感 | 読む |
| 番外編③|「やりたいことがない」は、問い直しの出発点 | やらない焦り/行動より問いを優先する選択 | 読む |
| 番外編⑩|「自分で決めたはずなのに、従っている感覚」 | 自分で決めた行動が“義務化”する違和感 | 読む |
| 第5話|揺れながらでも書いてみたら、“これまで”がつながった | 書くことで「やらない理由」が言語化された記録 | 読む |