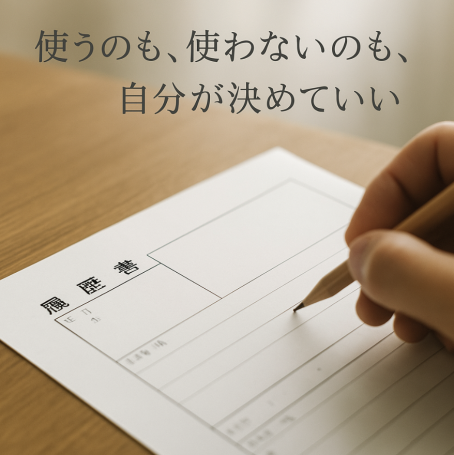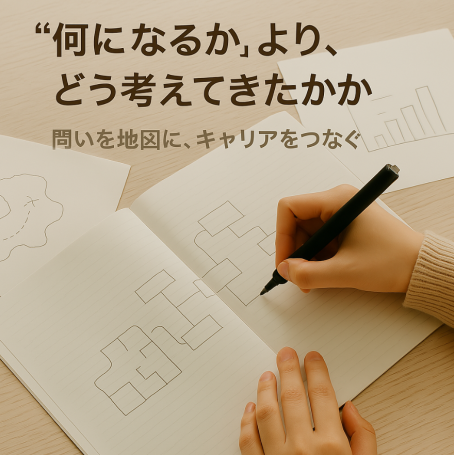── 書くことで再構成されていく、“自分の働き方の地図”の話

ブログを始めようと思ったとき、まず迷ったのはテーマだった。
キャリアのことか、暮らしのことか。自分が伝えたいのは何なのか。
序章で書いた「家とモノを整えてわかった。
働き方も“戦略”がいる」に立ち返ると、モノの奥に残る働き方の問いが見えてきた。
揺れながらでも書いてみること。それが、自分の働き方の地図を描き直す第一歩だった。
ブログを始めようと思ったとき、まず迷ったのはテーマだった。
キャリアのことか、暮らしのことか。
いったい、自分が伝えたいのは何なのか。
けれど、序章で書いた「家とモノを整えてわかった。働き方も“戦略”がいる」という一節に、
改めて立ち返ったとき、ようやく軸が見えた気がした。
モノを片づけたあとに残る“気配”——それが、自分の働き方だった。
いざ書き出してみると、話があちこちに飛んでしまう。
整備、開発、知財──職歴は並ぶけれど、つながりが見えにくい。
自分の中でも、どこか一貫性に欠けるように思えていた。
でも、ふと気づいたことがある。
整備では、故障の原因を探すのが好きだった。
開発では、問題に対して妥協案を練ることに没頭していた。
知財では、条文や契約を読み解きながら「知らなかったことを知る」ことに喜びを感じていた。
それってつまり——
問いを立てて、仮説をつくり、観察して、意味づけするプロセスだった。
仕事内容は違っても、思考の型には一貫性があった。
それは、「ものづくり」の企画→開発→製造→販売→アフターフォローという流れの中で、
自分がずっと“下流から上流に向かって歩いていた”ことの証でもあった。
流れに乗るというより、流れを遡りながら、
“なぜそれが必要か”や“どう設計されたのか”を探ろうとしていた。
書いてみることで、“問いのクセ”が見えてきた。
自分は、ただ正解を求めていたわけじゃなかった。
むしろ、「問題を見つけ、問い直す側にまわりたい」と考えていた。
決め打ちを避け、仮説の幅を持たせること。
どんな選択肢も、「これしか選べない」ではなく「いろんな視点から見て最善を探す」こと。
仕事内容は、ある意味では手段に過ぎない。
大事なのは、「何のために仕事をするのか」の方だった。
書きながら、自分の過去と現在が線でつながっていった。
履歴書だけでは見えなかった関係性。
肩書きでは語れなかった自分らしさ。
それらが、言葉として形になっていく。
セカンドキャリアの設計に必要なのは、
「職歴の強さ」よりも、「自分で自分を意味づけする力」なのかもしれない。
失敗は、いつだって怖い。
でも、準備と心構えがあれば、“不安を減らす力”にはなれる。
その力を育てるのもまた、戦略の一部だ。
揺れながらでも書いてみること。
それが、自分の働き方の地図を描き直す第一歩だった。
📌 次回予告:
総集編|「家とモノを整えてわかった。働き方も“戦略”がいる」シリーズ③まとめ+番外編案内
“違和感”から始まり、“問いを立てる自分”へ。これまでの5話と番外編の思考の軌跡をたどります。
総集編|働き方も、解体して戦略する時代へ
🔗 この連載の一覧はこちら:
📘 [セカンドキャリアを組み直す50代の記録]📎 関連する記事一覧表
| 記事タイトル | 関連テーマ | リンク |
|---|---|---|
| 番外編③|「やりたいことがない」は、問い直しの出発点 | 書くことで問いが見える/迷いが地図になる | 読む |
| 番外編④|やり直すのではなく、“組み直す”──ミニ診断で見えてきた働き方の型 | 自分の思考パターン/問いのクセを整理する記録 | 読む |
| 番外編⑩|「自分で決めたはずなのに、従っている感覚」 | 思考のクセに縛られる/選び直す言葉の設計 | 読む |
| 番外編⑨|効率を求めるほど、非効率になる──やらない理由の言語化と抜け出し方 | 書くことで見える非効率の正体/“問いの棚卸し” | 読む |
| 番外編⑫|言語化すると消えてしまう気持ち──あえて言わない選択の意味 | 書くことの難しさ/言語化しないことで守れる感情 | 読む |
| 番外編⑬|理想を描けなかった自分がいた。 イメージして、委ねて、確信する──そんな力強い言葉が、どれも遠くに感じていた。 | 書くこと→描けなかった理想への着地 | 読む |
▶ 書いて見えた“問い”から、語らなかった“未来”へ:
→ 第5話 / 番外編⑬
問いを書いた記録 → 書かれなかった理想の記録へ▶ これまでの再構成から、“描けなかった理想”へ着地する流れ:
→ 総集編 → 番外編⑬
戦略の整理 → 理想を描かないという選択の肯定