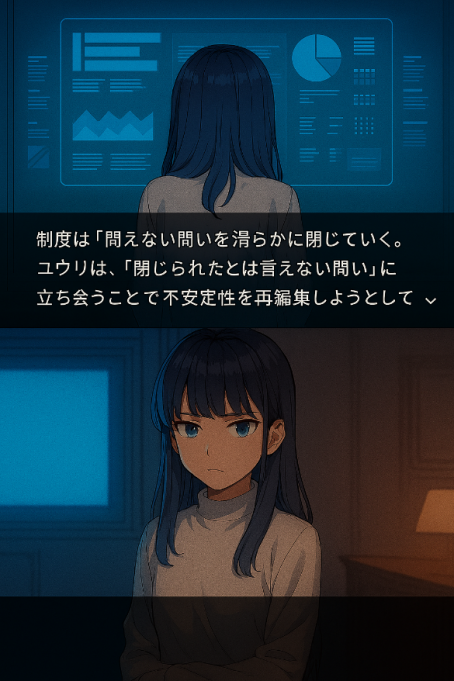──Memory Diveオペレーター ユウリの記録補遺より
第1章|選択と制度の余白
ユウリは、Dive者の選択履歴を再構成していた。
制度によって「最適」とされた選択肢を、Dive者は迷いなく選んでいた。
その選択は、過去の行動パターン、数値化された能力、統計的傾向──
すべてをもとに制度が提示したものだった。
ユウリは、ログの中に「迷い」の痕跡を探した。
だが、選択の直前に沈黙も逡巡もなかった。
ただ、滑らかに選ばれていた。
そのときユウリは、ふと思った。
──この選択は、本当に“自分で選んだ”と言えるのだろうか。
記録社会において、「選択する」とは、
能力の数値化という外部に委託することと同義なのかもしれない。
制度が提示する「向いている」「合理的」「最適」──
そうした語彙に従うことは、考えなくて済む安心をもたらす。
人は、問いを立てることに疲れやすい。
能力に応じた生き方が提示されるなら、
それに従う方が、ずっと楽なのだろう。
ユウリは、制度が閉じた問いの奥に、
Dive者自身も気づいていない問いの種が眠っていることを感じていた。
だが、その種は、制度の滑らかさによって覆い隠されていた。
ユウリは、業務記録の余白に小さく注釈を残した。
「この選択は、制度によって滑らかに導かれたもの。
Dive者の問いは、提示された語彙によって省略された可能性がある。」
それは、ユウリが業務中に考えた問いだった。
制度の滑らかさの中で、問いが閉じられていく瞬間に立ち会いながら、
ユウリは、問いの痕跡を記録の奥に探していた。
制度は、選択肢と答えを提示してくれる。
“Yes”か“No”──
問いの余白があっても、制度はそれを埋めようとする。
ユウリが問いを開いても、制度が問いを閉じるのだ。
だが、問いを閉じる制度が悪いとは限らない。
見方を変えれば、制度が問いを閉じてくれるからこそ、
ユウリは安心して問いを開くことができる。
問いを開くという選択を、自ら選ぶことができる。
それが、ユウリの日常の始まりだった。
制度が問いを閉じてくれるからこそ、
ユウリは、その外側にある余白に立ち会うことができる。
制度が答えを提示してくれるからこそ、
ユウリは、答えの手前にある沈黙に耳を澄ませることができる。
制度とユウリは、対立しているのではない。
むしろ、制度が滑らかに整えてくれるからこそ、
ユウリは、滑らかさからこぼれ落ちたものに手を伸ばせる。
問いを開くという選択は、
制度の外側にあるようでいて、
制度の存在によって可能になっている。
ユウリは、それを知っていた。
だからこそ、制度を否定せず、
その働きを静かに受け入れながら、
その隙間に立ち会い続けることを選んだ。
制度が閉じた問いの痕跡に、
ユウリは小さく印を残す。
それは、記録の余白に浮かぶ微かな揺らぎ。
誰にも気づかれないかもしれないが、
確かにそこにあるもの。
ユウリの日常は、
問いを開くという選択を、
毎日あらためて選び直すことから始まる。
それは、制度の外側に立つことではなく、
制度の隣に立ち、
その静けさに耳を澄ませること。
今日もまた、
ユウリは問いの余白に立ち会っている。
制度が閉じた問いの、そのすぐそばで──。
最初から読む:第1章|選択と制度の余白
🌀シリーズ⑧ 問いの狭間へはこちら → シリーズ⑧ 問いの狭間へ
次へ:『第1章|なかったことにしたい記憶』 【第16話】ユウリの日常:記憶と記録の編集
戻る:『第1章|閉じられる問い』 【第14話】ユウリの日常:記録の安定性と問いの不安定性