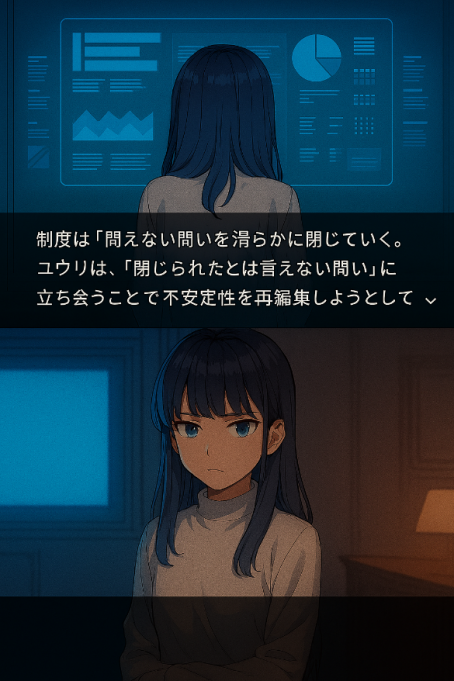
──Memory Diveオペレーター ユウリの記録補遺より
第1章|閉じられる問い
ユウリは、記録の再構成業務の途中だった。
制度によって「合理的な選択」と分類されたDive者の行動ログを確認していたが、
その選択の直前に、わずかな沈黙があった。
選択肢は三つ。
制度は、そのうちの一つを「最適」として強調していた。
Dive者は、迷いなくそれを選んだ。
ユウリは、その「迷いのなさ」に違和感を覚えた。
選択肢の提示順、色彩、過去の履歴との照合──
すべてが制度によって滑らかに設計されていた。
Dive者は、制度の導きに従っただけだった。
だが、記録には「自分で選んだ」と記されていた。
そのとき、ユウリはふと考えた。
──記録社会において、選択とは何なのか。
それは、制度が整理した選択肢の中から、
最も合理的なものを選ぶことなのか。
それとも、制度が提示した選択肢に従うことを、
「自分で選んだ」と感じる構造そのものなのか。
ユウリは、記録の奥に沈んでいた問いに触れた。
その選択の手前に、問いはあったのか。
それとも、制度が問いを閉じていたのか。
彼女は、記録の余白に小さく注釈を残した。
「この選択は、制度によって滑らかに導かれたもの。
Dive者の問いは、制度の提示によって省略された可能性がある。」
それは、ユウリが業務中に考えた問いだった。
制度の滑らかさの中で、問いが閉じられていく瞬間に立ち会いながら、
ユウリは、問いの痕跡を記録の奥に探していた。
記録社会において、選択とは──
能力の数値化という外部に委ねられた判断のことかもしれない。
制度は、個人の思考を代行してくれる。
制度は、選択肢を整理し、判断基準を提示し、
「何を選ぶべきか」「どう振る舞うべきか」を滑らかに導いてくれる。
その結果、個人は複雑な思考を省略し、制度の提示に従って行動できる。
つまり──
制度は、問いを立てる前に答えを提示することで、
個人が「考える」手前のプロセスを肩代わりしているのだ。
制度は、あらかじめ選ばれた選択肢を並べることで、「何を考えるか」を限定する。
たとえば、職業紹介制度では「この中から選んでください」と言われるが、
「なぜ働くのか」は問われない。
制度は、行動や記録にタグを付けて分類することで、「どう考えたか」を構造化する。
「衝動的」「目的不明」「計画的」──
そうしたラベルが、個人の思考の痕跡を制度的に処理していく。
制度は、過去の履歴や統計に基づいて「最も合理的な選択肢」を提示する。
それに従えば、個人は「なぜそれを選ぶのか」を深く考えなくても済む。
人は、考えることに疲れやすい。
能力に応じた生き方を提示されれば、
それに従うという選択を“自分で選んだ”と感じる。
現代社会では、選択肢が過剰に提示される。
進路、職業、生活様式、価値観──
すべてが「自由に選べる」とされるが、
それは同時に「自分で決めなければならない」という負荷を伴う。
何を選ぶか以前に、「何を問うか」を考えることは、
深い内省と葛藤を伴う。
人はその問いの生成に疲れてしまう。
選択の自由があるとされる一方で、
結果の責任はすべて個人に帰属する。
これもまた、思考の重さを増す。
制度は、個人の過去の履歴・能力・傾向をもとに、「最適な生き方」を提示する。
「あなたにはこの職業が向いています」
「このライフスタイルが合っています」──
それは、選択肢を絞り、思考の負荷を軽減する。
つまり、制度は「問いを立てる前に答えを提示する」ことで、思考を代行してくれる。
たとえば、3つの職業から1つを選ぶとき、
「自分で選んだ」と感じるが、
そもそもその3つが誰によって選ばれたかは問われない。
疲れた状態では、「考えなくて済むこと」が安心につながる。
提示された選択肢に従うことは、負荷の少ない選択であり、
むしろ「自分らしい」と感じられる。
「向いている」「合っている」「合理的」──
そうした語彙が、制度から個人へと移行し、
自分の判断のように感じられる。
制度は問いを閉じてくれる。
だから、考えなくて済む。
それは、ある種の優しさでもある。
制度の答えは、“Yes”か“No”。
問いの余白があっても、制度はそれを埋めてくれる。
滑らかに、確実に、迷いなく。
ユウリは時折、問いを開こうとする。
彼女は、制度が提示した選択肢の外側にある「問いの余白」に立ち会う編集者だ。
Dive者が「自分で選んだ」と感じている選択の奥に、
制度が先回りして提示した語彙や構造を見抜いている。
つまり──
ユウリは、「選んだ」という感覚の背後にある「選ばされた構造」に立ち会い、
その沈黙や迷いに意味の居場所を与えようとしている。
だが、制度はその問いを閉じていく。
それは、制度の役割であり、記録の安定性のためでもある。
一見すると、考えていないように見えるかもしれない。
けれど、ユウリは思う。
「それは、悪い選択ではない。」
少なくとも──
問いを開こうとするかどうかを、自分で考えたという事実がある。
その選択の手前に、確かに思考があった。
制度に委ねることもまた、問いのひとつなのだ。
ユウリは今日も、問いの余白に立ち会いながら、
制度が閉じていく問いの痕跡を、静かに見送っている。
最初から読む:第1章|閉じられる問い
🌀シリーズ⑧ 問いの狭間へはこちら → シリーズ⑧ 問いの狭間へ
次へ:『第1章|選択と制度の余白』 【第15話】ユウリの日常:問いを閉じる制度、問いを開く日常
戻る:『第1章|語られなかった目的』 【第13話】ユウリの日常:問いの消失と目的の残響

