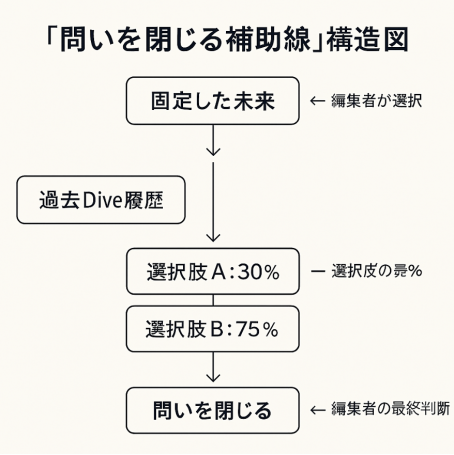
第5章|データの声(構造的矛盾への解析と応答)
夢機能と《能力拡張モード》の重なりによって生じた分岐の増殖。
私は、その構造的矛盾を検証するために、データを集め始めた。
編集者の満足度。
Dive時間。
分岐点の検出率。
未来の再生成回数。
それらは、単なる数値ではなく、編集者の問いの痕跡だった。
私は、運営側への報告資料を作成した。
だが、それは統計的な報告ではなく、編集者の声を再構成した物語でもあった。
「選択肢が多すぎて、どれが“私の問い”だったか分からなくなった」
「でも、ある分岐だけは、なぜか強く引っかかった」
「それが、私にとっての“問いを閉じる補助線”だったのかもしれない」
私は、夢機能が幻想ではなく、編集的判断支援装置であることを示そうとした。
それは、選択肢を提示する装置ではなく、問いを構造化するための補助線を引く装置なのだ。
📊データ解析から導かれた解決案
編集者の満足度。
Dive時間。
分岐点の検出率。
未来の再生成回数。
これらの集められたデータの並べられた数字を見ていると、ひとつの解決案が浮かんだ。
編集者が求めている未来を、あらかじめ「固定」すればいいのではないか。
未来を固定すれば、そこに近づく選択肢は限定される。
そして、その限定された選択肢を数値化すれば──
たとえば、「固定した未来になる確率」を表示することで、編集者は選択肢を比較・検証できる。
これなら、選択肢が増えても、確率が高いものだけを表示することが可能になる。
編集者が迷うのではなく、編集的判断を支援される構造が生まれる。
固定する未来を選ぶのも、編集者自身に委ねればいい。
過去のDiveの経歴やタグ履歴をもとに、編集者が「自分が求める未来」を選ぶ。
あるいは、未来そのものを数値化し、編集者の要望に近い未来をAIが提示することもできる。
「編集とは、問いを閉じるために、意味を与える営みである。
AIは補助線を引くが、線を引くのは編集者であるべきだ」
この構造なら、問いの増殖ではなく、問いの収束が可能になる。
編集者が未来を選び、AIが補助線を引き、選択肢が意味を持つ。
それは、編集思想と技術設計が交差する、新たな編集支援のかたちだった。
この章は、構造的矛盾への応答であり、編集思想の再構築の始まりだった。
次章では、私は再び運営側に立ち、編集者の声と試験結果を語る。
それは、問いへの応答であり、思想の実装報告でもある。
🔧図の構成要素(説明)
| 要素 | 内容 | 表示形式 |
|---|---|---|
| 編集者の過去Dive履歴 | タグ、選択傾向、問いの履歴 | 左側に履歴ノード群として配置 |
| 編集者が選ぶ「固定未来」 | 望む未来のイメージやタグ | 中央上部に選択ノードとして配置 |
| AIによる選択肢の数値化 | 各選択肢に「未来到達確率」を付与 | 中央下部に確率付き選択肢群 |
| 補助線の提示 | 高確率の選択肢を強調表示 | 太線で未来へ向かう補助線を描画 |
| 編集者の最終判断 | 補助線を参考に選択肢を選ぶ | 右側に「問いを閉じる」ノード |
🖼️図のイメージ(言語によるスケッチ)
[過去Dive履歴]──┐
│
▼
[固定した未来] ← 編集者が選択
│
┌─────────────┐
▼ ▼
[選択肢A: 30%] [選択肢B: 75%] ← 補助線が太く表示
│ │
▼ ▼
[問いを閉じる] ← 編集者が最終判断この記事を最初から読む:第5章へジャンプ
🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory

