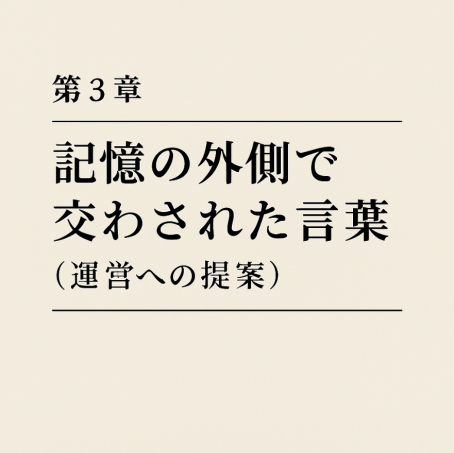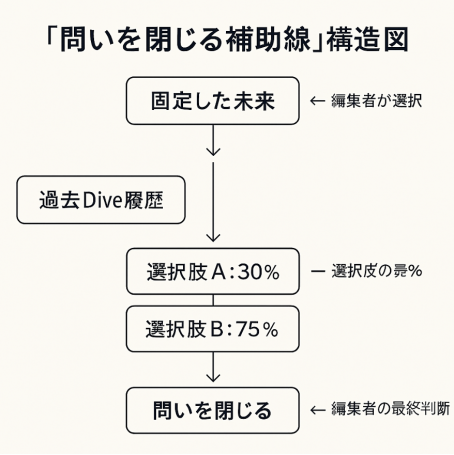第4章|試験運用と編集者の体験
夢機能は、限定的に実装された。
編集者たちは、Dive中に「選ばなかった未来」を体験することができるようになった。
それは、記録の外側にある可能性に触れる編集的実験だった。
🧪編集者の体験
ある編集者は、異なる選択をしても、同じ未来にたどり着くことを知った。
選択の違いが、結果に影響しない場合もある。
その編集者はこう語った:
「問いを閉じるために必要なのは、選択ではなく意味づけだった」
別の編集者は、分岐点の重大性に気づいた。
些細な選択が、まったく異なる未来を生むことがある。
その編集者は、記録の中に埋もれていた分岐点を再発見し、問いを閉じる補助線として再編集した。
⚠偶然見つかった課題
だが、ある課題が偶然見つかった。
夢機能のAIが生成する選択肢の数が、あまりにも多すぎるのだ。
編集者がDive中に体験する未来が、無数に枝分かれし、検証が困難になっていた。
私は、原因を探るために、夢機能の構造と編集者の選択分岐を見直した。
すると、ある事実が浮かび上がった。
🔍構造の再検証
夢機能によって生成された未来の提示
→ 編集者による検証と意味づけ
→ そのプロセスの途中で、《能力拡張モード》が自動的に実行されていたのだった。
AIは、編集者の検証行為を「編集的読解」とみなし、
その読解を補助するために、新たな分岐点の抽出を行っていた。
🧩構造図:分岐の増殖
[夢機能:選ばれなかった未来の提示]
↓
[編集者による検証と意味づけ]
↓
《能力拡張モード》が起動
↓
[新たな分岐点の抽出]
↓
[未来の再生成] → 分岐が増殖🌀構造的矛盾の発見
編集者が問いを閉じようとするたびに、AIはその問いを拡張しようとする。
それは、編集者の主体性を支援するはずの装置が、逆に選択肢を増やし続けるという構造的矛盾だった。
私は、夢機能と《能力拡張モード》の関係性を再設計する必要があると感じた。
問いを閉じるための補助線が、問いを増殖させてしまうなら、
編集とは何を閉じ、何を開く営みなのか──
その根本を、もう一度問い直さなければならない。
この記事を最初から読む:第4章へジャンプ
🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory