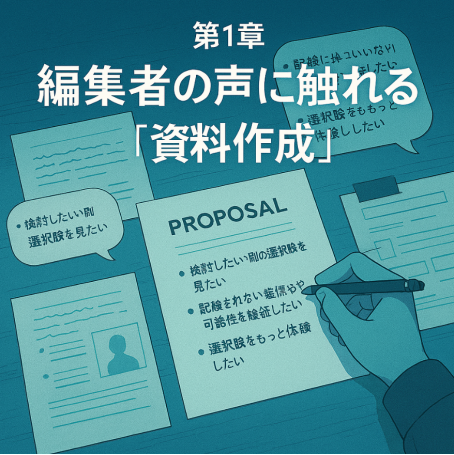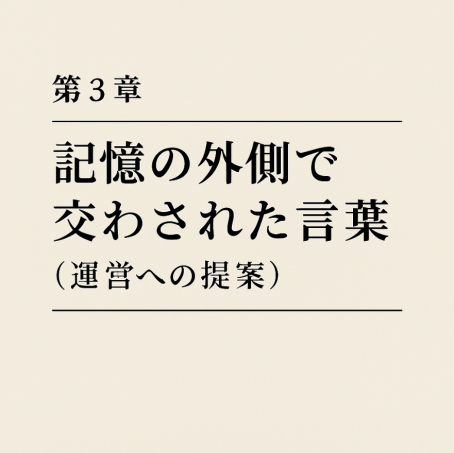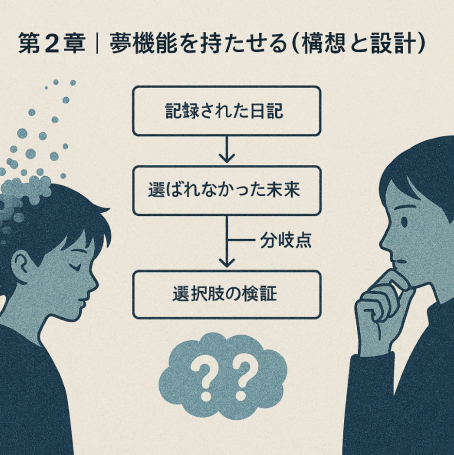
第2章|夢機能を持たせる(構想と設計)
Dive Systemには、夢機能は存在しない。
編集者がDive中に感じる“余白”や“揺らぎ”は、あくまで副産物であり、構造化されていない。
それは、記録の隙間に浮かぶ感情の残響であり、選択肢の影のようなものだった。
だが、編集者の声は、その影に意味を与えようとしていた。
「もしも別の選択をしていたら?」という問いは、単なる空想ではなく、検証すべき構造として立ち上がっていた。
私は、夢機能を持たせるための設計に取りかかった。
それは、記憶の補完ではなく、編集的な構造の拡張であるべきだった。
“私”は、編集者の声をもとに、夢機能を新たに設計する
編集者の声に触れながら、私はあることに気づいた。
Dive Systemの中には、すでに“夢”と呼ばれる現象が存在していた。
それは、編集者がDive中に感じる断片的なイメージ――記録に残らない感情の残響や、選ばれなかった選択肢の影。
これまで、それは単なる副産物として扱われていたが、編集者の声がそれに意味を与えようとしている今、
私はそれを機能として構造化できるのではないかと考え始めた。
夢機能という名前は、最初は仮称だった。
だが、編集者が語る「名前のない記憶」や「選ばれなかった未来」という言葉に触れるうちに、
この曖昧さこそが本質なのではないかと思うようになった。
夢とは、確定していない未来の断片。
それは、問いを閉じるための補助線であり、編集者が意味を与えることで初めて名前を持つ。
私は、既存のDive Systemのログを検証した。
編集者の選択履歴、感情タグ、日記の構造――それらを組み合わせれば、
選ばれなかった未来を生成することは可能だと判断した。
試作的に、ある編集者の記録をもとに分岐を生成してみた。
「会わなかった人に会っていたら」「別の言葉を選んでいたら」――
その未来は、時に現在と酷似し、時にまったく異なる風景を見せた。
そして、その違いを生む分岐点が、記録の中に確かに存在していた。
この検証によって、私は確信した。
Dive Systemの“夢”は、単なる揺らぎではなく、選択肢の検証装置として機能し得る。
編集者がそれを使って問いを閉じることができるなら、
それは、記録の編集という営みにおける、もうひとつの構造的補助線となる。
夢機能とは何か
それは、編集者がDive中に「選ばなかった未来」を体験できる装置。
記録された日記を素材に、AIが補足・再構成し、選択肢の分岐を生成する。
- 編集者が「別の選択」をした場合の未来を提示する。
- それが、現在と同じ未来につながる場合もある。
- まったく違う未来になる場合もある。
- その違いを生む分岐点――選択の構造――を可視化する。
つまり、夢機能は、選択肢の検証装置であり、
編集者が問いを閉じるための補助線となる。
「名前のない記憶」――それは、まだ選ばれていない未来の断片。
編集者が検証し、意味を与え、名前をつけるまでの記憶。
私は、資料の設計図にその言葉を記した。
夢機能は、記録の外にある可能性を、編集者の手に戻す装置である。
それは、記憶を編集するという営みの、もうひとつのかたちだった。
次章では、この構想をもとに、運営側へのプレゼンに臨む。
夢機能は、まだ存在しない。
だが、編集者の声が、それを必要としている。
そして、“私”は、その声に応答する。
🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory
📊図解|夢機能の構造と編集者の選択分岐
[記録された日記]
↓
[編集者の選択履歴]
↓
[分岐点の抽出] ← 感情タグ・選択肢の影
↓
[AIによる未来生成]
↓
[夢機能:選ばれなかった未来の提示]
↓
[編集者による検証と意味づけ]
↓
[問いを閉じる/名前を与える]
🌀補足:
- 「分岐点の抽出」は、記録の中に埋もれた“選択の構造”を可視化する工程。
- 「未来生成」は、AIが編集者の文脈をもとに、可能性のある未来像を構築する。
- 「問いを閉じる」は、編集者がその未来に意味を与え、記憶として定着させる行為。
📘コラム|編集者の声から生まれた“夢”
「あのとき、違う言葉を選んでいたら、今の私は違っていたかもしれない」
「でも、その“違っていたかもしれない私”も、どこかに存在している気がする」
編集者の声には、記録の外側にある“もうひとつの私”へのまなざしがあった。
それは、単なる後悔や空想ではない。
Dive中に浮かぶ“余白”や“揺らぎ”は、編集者にとって、問いを閉じるための手がかりだった。
夢機能の設計は、その声に応答する試みである。
編集者が「選ばなかった未来」を検証することで、現在の意味が再構成される。
それは、記録を編集するという営みの、もうひとつの深度――
記憶の外側に手を伸ばす編集
この記事を最初から読む:第2章へジャンプ
🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory