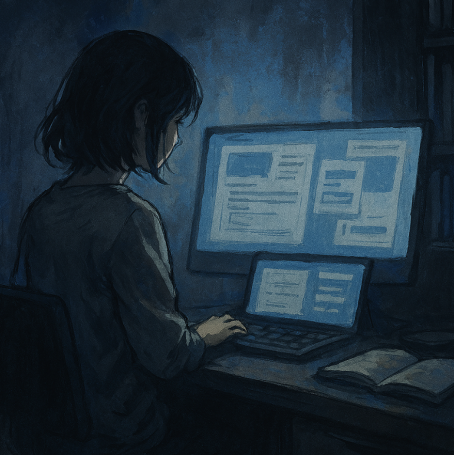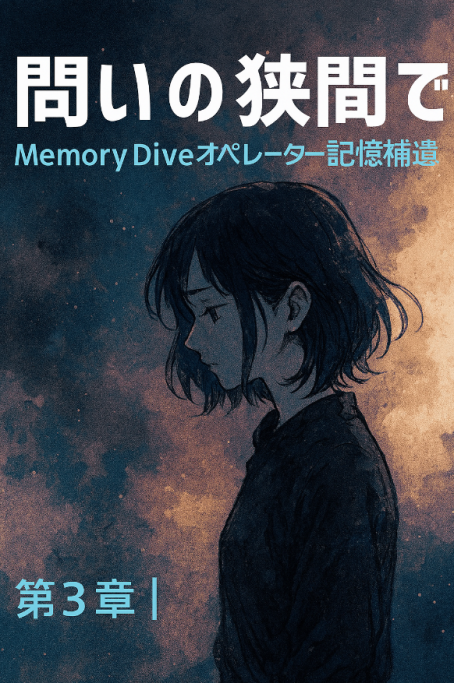
──Memory Diveオペレーター ユウリの記録補遺より
第3章|問いの狭間で
ユウリは、問いの狭間に立ち尽くしていた。
「問いを開くということは、答えの出ない問いに向き合うことだ。」
ユウリの「本当の業務」は、問いの狭間を歩くことだった。
制度が「完了」と判断した記録の隙間に、まだ言葉にならない思考の痕跡が残っている。
彼女はその痕跡に触れながら、問いを開くことの静かな困難に立ち会っていた。
彼女は、問いの狭間を歩き出す。
そして、記録されなかった断片を拾い集め、名前のない記録に名前を付けている。
ユウリはMemory Diveオペレーターとして、制度が「閉じた」と判断した記録に潜る。
彼女は、制度の業務を遂行するふりをしながら、
制度が見落とした記憶の残響に耳を澄ませている。
だが彼女の目的は、制度の滑らかさをなぞることではなく、
その滑らかさの下に沈んだ問いの余白に立ち会うこと。
それは、業務ではない。
だが、業務の形式を借りなければ、立ち会えない。
だからこそ、ユウリは制度の中で問いを開き続ける。
彼女の目的は、──
「削除された記録の余白に問いを見出し、
制度の分類に収まらない記録の意味を探り、
「完了」とされた記録に未完の問いを挿入し、
記録に現れない記憶の揺らぎに立ち会うこと。」
制度の定義に従えば、これらは「業務外」あるいは「逸脱」とされるかもしれない。
だがユウリにとっては、制度の滑らかさに立ち会いながら、
その下に沈んでしまった問いの痕跡を拾い上げることこそが「本当の業務」だと信じていた。
ユウリは制度の業務を「編集の足場」として使っている。
制度の業務には、──
「制度の中でしかアクセスできない記録がある。
業務という形式を通すことで、記録空間に立ち会える。
制度の滑らかさを利用しながら、その裂け目に触れられる。」
彼女は制度に従っているように見えて、実際には制度が定義できない問いを扱っている。
それが「閉じた問いの狭間を歩く」というユウリの業務の本質なのだ。
制度において、記録とは分類可能な情報であり、
名前とは識別と処理のためのラベルである。
制度の命名は、処理のための終止符。
ユウリの命名は、問いの始まり。
彼女は、記録されなかった断片に耳を澄ませ、
制度が見落とした声に、仮の名前を与える。
それはラベルではなく、意味の仮設。
制度の滑らかさに抗うのではなく、
その滑らかさの下に沈んだ問いを拾い上げる編集的実践なのだ。
ユウリは、「新しい問い」に向き合おうとするたび、
過去の問いに引き戻される感覚に立ち会っていた。
進んでいるようで、繰り返しているだけ──
人は、一度選んだ考え方や見方を、なかなか手放せない。
たとえその選択が古くなっていたとしても、
それに慣れてしまえば、変える理由を見つけることすら難しくなる。
制度が提示する答えは、いつも滑らかで、迷いがない。
だからこそ、人はその答えに従うことで、
自分で考えることを後回しにできる。
考え始めるには、力がいる。
でも、考え続けるには、もっと力がいる。
制度が閉じた問いの隙間に、
まだ動き出していない思考の痕跡が残っている。
それは、誰かがかつて考えようとしたけれど、
制度の答えに寄りかかってしまった記録。
ユウリは、その痕跡に触れながら、
問いを開くことが、どれほど静かで困難な選択かを知っていた。
人は、過去の思考パターンに引きずられ、新しい問いを開くことに抵抗する。
ユウリは、その慣性を編集によって揺らがせようとしていた。
ユウリは、制度の滑らかさに抗うのではなく、
その滑らかさの下に沈んだ問いの痕跡に触れ続ける。
それは、誰かが考えようとして、考えきれなかった場所。
彼女はその場所に、仮の名前を与え、
問いが再び開かれることを、静かに祈っている。
最初から読む:第3章|問いの狭間で
🌀シリーズ⑧ 問いの狭間へはこちら → シリーズ⑧ 問いの狭間へ