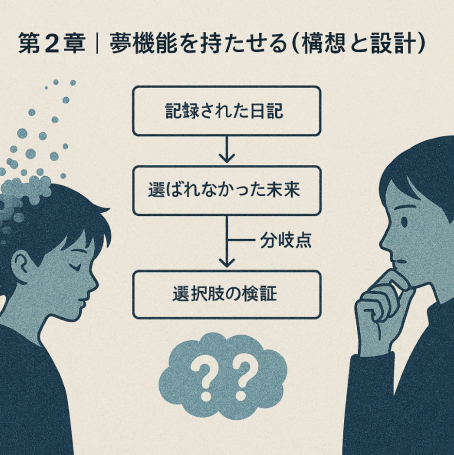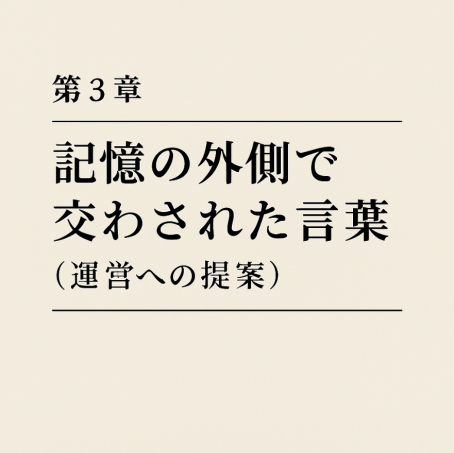
第3章|記憶の外側で交わされた言葉(運営への提案)
会議室は静まり返っていた。
Memory Diveの運営チームが並ぶ長机の向こうに、私は立っていた。
手元には、夢機能の提案資料。だが、それを読み上げるつもりはなかった。
私は、編集者の声を語ることにした。
それは、機能説明ではなく、記録と記憶の間に生まれた物語だった。
「あの時、別の選択をしていたらどうなっていたかを見たい」
「記録に残っていない感情や可能性を検証したい」
「問いを閉じるために、もっと選択肢を体験したい」
これらの声は、単なる感想ではない。
編集者が記録の外側にある“名前のない記憶”に意味を与えようとする、編集的欲求そのものだ。
そのために、夢機能が必要なのだと私は語った。
資料には、分岐の例を載せた。
ある編集者が「会わなかった人に会っていたら」と語った記録。
AIが生成した未来は、現在と酷似していたが、感情のタグがまったく異なっていた。
その違いが、問いを閉じるための補助線になる。
🧭運営側の懸念と応答
運営側から、懸念の声が上がった。
「それは記憶の改変ではないか?」
「倫理的な問題はどう考える?」
「《能力拡張モード》と何が違うのか?」
私は、ひとつずつ応答した。
《能力拡張モード》との違い
- 《能力拡張モード》は、記録の「内側」を深く掘る装置。
- タグの補完、感情の分析、構造の可視化などを通じて、過去をより明晰にする。
- 編集者の読解力や構造化能力を支援する補助線である。
一方、夢機能は記録の「外側」に補助線を引く装置である。
編集者が「もしも」を検証するために、選ばれなかった未来を仮想的に生成する。
それは、記録の補完ではなく、問いを閉じるための編集的実験だ。
倫理的な問題への応答
夢機能は記憶の改変ではない。
だが、仮想体験があまりにリアルである場合、編集者が現実と混同するリスクがある。
また、生成された未来が「より良い選択肢」に見えることで、現在の記録に対する否定的感情が生まれる可能性もある。
だからこそ、夢機能には編集者の主体性を守る設計が必要だ。
AIは補助線を引くだけであり、編集の主導権は常に編集者にある。
使用には明確な目的と同意が必要であり、心理的な安定性も考慮されるべきだ。
🎙対話ログ|プレゼン後のやりとり
運営A「編集者が“より良い未来”を見てしまった場合、今の記録を否定することになりませんか?」
私「否定ではなく、検証です。“今”を確かめるために、別の可能性に触れるのです」運営B「でも、現実との混同が起きたら?」
私「だからこそ、“記録とは異なる”と明示されます。編集者の主体性を守る設計が必要です」運営C「《能力拡張モード》で十分なのでは?」
私「それは記録の内側を深く掘る装置です。夢機能は、記録の外側に補助線を引く装置です」運営A「つまり、編集者が“問いを閉じる”ための実験装置?」
私「はい。それが、Memory Diveの次なる編集思想です」
📘補足コラム|問いを閉じるための“夢”と“責任”
夢機能は、編集者の問いに応答する装置である。
だが、それは単なる技術的補助ではない。
編集者が「選ばなかった未来」に触れるということは、
現在の記録に対する再解釈と、自己への再編集を意味する。
それは、記憶の外側に手を伸ばす行為であり、
同時に、編集者自身がその手の届く範囲と責任を引き受けることでもある。
夢を見ることは、問いを閉じるための補助線である。
だが、その補助線をどう引くかは、編集者自身の選択に委ねられている。
Memory Diveは、記録を保存する場所ではなく、
問いを閉じるための構造を編集者に提供する場である。
夢機能は、その構造の外縁に差し込まれる、もうひとつの編集線なのだ。
🌀プレゼンの余韻
「問いを閉じるために、夢を見る」
それが、Memory Diveの次なる編集思想です。
私はそう語り、プレゼンを終えた。
沈黙のあと、運営側のひとりが言った。
「それは、記録の外側にある編集ですね」
私はうなずいた。
夢機能は、まだ存在しない。
だが、編集者の声が、それを必要としている。
そして、“私”は、その声に応答した。
この記事を最初から読む:第3章へジャンプ
次章へ:第4章|試験運用と編集者の体験
🧠 シリーズ⑦『名前のない記憶』はこちら → nameless-memory