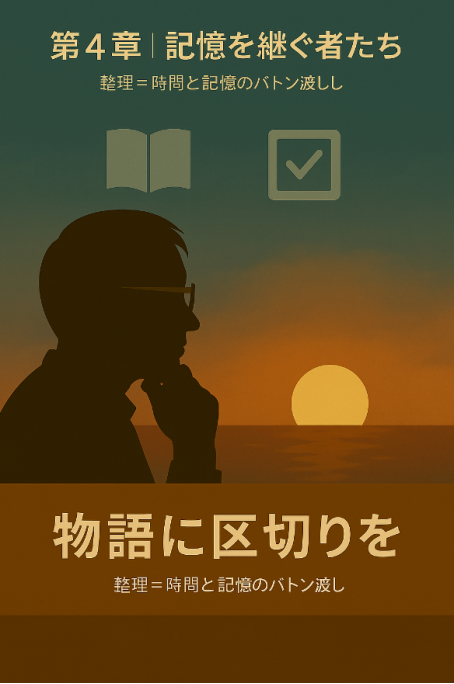──AI社会で、「人間にしかできない編集」とは何か?
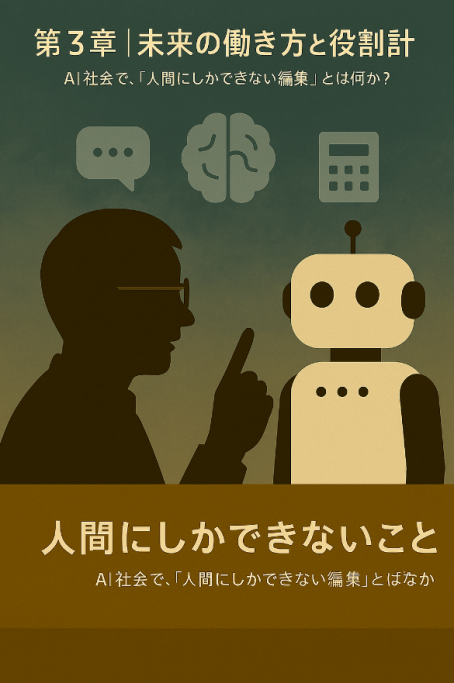
🤖 働くって何だ?AIと並ぶ時代に見つける“自分の役割”
このブログはAIと一緒に書いています。
AIを使い始めたのは退職後ですが、会社員時代に導入されていたら……どれだけ仕事がラクだったかと、今さら思うことがあります。
けれど、そんな状況でも上司はこう言ったでしょう。
「仕事が早く終わったなら、別の仕事をしなさい」
従業員を効率化したい会社。
何とかラクしたい従業員。
この構図は、AIがいようがいまいが、きっと変わらない。
もっと顕著なのが「定年延長制度」。
業務量は変わらず、給料は半分。
いわゆる“老害”と呼ばれる人も生まれてしまう構造です。
でも実際には、業務量そのものが少ない定年間際に、
業務量と同じくらいの給料に戻っただけという見方もあるのです。
そんな社会のねじれを見てきた今、私はこう感じます。
AIは優秀です。
でも「優秀だけど融通が効かない」のが、今のところの印象です。
✨編集者という人間の役割
質問には何でも答えてくれる。
情報を集め、整理し、必要な要点までまとめてくれる。
AIは、編集者の右腕としては申し分ない性能です。
「ポジティブな意見だけにして」
「批判のコメントは除いて」
そんな指示にも、きちんと応えてくれます。
ただ、それでも最終的に“決める”のは人間です。
情報が膨大すぎる時代だからこそ、
人間が担う役割は「選択」と「意味づけ」だと思うのです。
なぜこのモノを残すのか?
なぜこの言葉で語るのか?
この問いに向き合うのは、人間しかできない仕事です。
🪞50代からの“役割再構成”
人生前半は、「与えられた肩書きをこなす」ことで働いてきました。
会社員・親・専門職・管理者──どれも大切な役割でした。
でも、50代からは「肩書きの外側」を見直す時期です。
空き家整理を経験したように、
私たちは“暮らしの外殻”だけでなく“役割の中身”も再構成し始めることになります。
社会に何を渡せるか。
誰のために、何を語るか。
その問いは、単なるキャリアの再設計ではなく、
“文明の中で果たす責任”としての働き方へとつながっていきます。
🧭AIと共鳴する働き方へ
AIが進化するほど、人間にしかできない仕事は絞られていくように感じます。
けれど、その“限られた仕事”は、どれも本質的です。
- 感情の余白を読み取り、言葉を添える
- 物語の奥にある構造を見抜く
- 境界線を見つけ、橋を架ける
そういった行為こそが、文明という物語において“人間に任されている編集”なのです。
これからの働き方は、
効率や肩書きの延長ではなく、
自分自身を“編集者”として再定義することにあるのかもしれません。
🔜 次章は最終章|空き家・記憶・働き方のすべてがつながるエピローグへ。
「千年の舞台に挑む編集者」としての物語を締めくくっていきます。
▶️ シリーズ④の記事一覧はこちら:
千年の舞台に挑む編集者たち|境界を超える整理の哲学